学修に関する総合相談窓口
休学や退学に関する悩み、転学部・転学科など、学修全般に関することについて、学生本人はもちろん、保護者の方からのご相談にも応じています。学修に関する悩みがある場合は、教育開発支援センターへ気軽にご相談ください。
教育開発支援センターの取り組み
教育開発支援センター
~学生の視点に立つ教育改善~

経営学部教授
教育開発支援センターは、本学の「建学の精神」に基づく大学教育の改善を目的に、平成18年10月に開設されました。
本学学生の視点に立ち、社会のニーズに対応するための教育システム開発の研究部門、それらを実践かつ支援する教職員支援部門、学生の学修を支援する部門の3部門の教育支援の活動を行っています。
これらの支援活動を通して、学生にとって、
- ①「わかりやすく確実に学力がつく講義」
- ②「充実した学生生活」
- ③「豊かな将来の保証」をめざしています。
教育の四つの柱(教育ビジョン)
- 四年間一貫した少人数ゼミナール(人間力教育と専門教育)
- 確かな学力と充実した学修支援
- 一人ひとりに応じた魅力的なキャリア教育支援
- 英語力を確実に伸ばすプログラム
学修支援
教育開発支援センターは学生の4年間の学修を見守ります。
大学で学ぶということ―「覚える」勉強から「考える」勉強へ
高校までは、教えてもらったことを、事実として「覚える」ことが勉強でした。大学では明らかな答えが存在しない問題や答えがたくさんある問題も扱うので、「覚える」ことよりも、「考える」ことが中心となります。自分で問題を発見し、自分で調べ、自分なりの答えを出すという「主体的に学ぶ」ことが求められます。
この求められる姿勢の違いは、中学・高校生が「生徒」と呼ばれ、大学生が「学生」と呼ばれることにも表れています。初年次教育では、この「学びの転換」をはかる重要な役割を担っています。
大阪学院大学の初年次教育について
「フレッシュマンスキル」
この科目はキャリアデザインからの視点で行う初年次教育です。大阪学院大学の建学の精神、学部・学科の教育目的、学位授与方針、教育課程編成・実施の方針を理解します。アカデミックスキルはもちろん、本学の施設設備を活用し、充実した大学生活について学びます。 この科目は、「OGU教育」(1単位)と同様、初年次生は履修しなければいけない科目です。1年次後期から始まる「キャリアデザイン科目」に先立ち、社会人基礎力を養成します。



フレッシュマンスキルの様子
初年次生対象教育懇談会
5月に「初年次生対象の教育懇談会」を開催し、ゼミ担当教員と保護者・学生との懇談を行っています。 2025年度は、5月17日(土)に開催しました。
2025年度 初年次生対象の教育懇談会 開催報告



キャリア教育(体系的なキャリアデザイン)
キャリア教育は、「キャリアデザイン入門Ⅰ」(1年次後期2単位)、「キャリアデザイン入門Ⅱ」(2年次2単位)、「キャリアデザインⅠ」(2年次2単位)、「キャリアデザインⅡ」(2年次2単位)、「キャリアデザインⅢ」(3年次2単位)の計5科目で構成されています。
また、学生の進路に応じたキャリア形成を選択できるように、企業、公務員、教員向けのクラスをそれぞれ開講しています。また「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」、「キャリアデザインⅢ」には「女子専用クラス」を設けています。「キャリアデザインⅠ」はSPI等、「キャリアデザインⅡ」は自己PR・面接、「キャリアデザインⅢ」は業界研究を行っています。
さらに、キャリアデザイン科目では、アクティブ・ラーニングやPBL(Project-based learning)を取り入れ、学生が主体的に学べるような学習法を取り入れています。
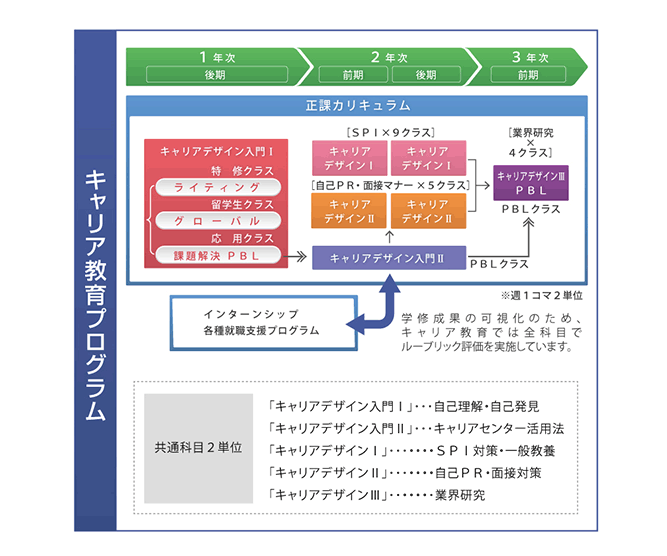
履修者の声

キャリアデザインの授業を通して、自分の意見を明確に伝える力が身についたと実感しています。また、グループディスカッションや発表を重ねることで、人前で話すことへの抵抗が減り、自信を持って発言できるようになりました。特に、面接練習では、採用担当者が注目するポイントを実践的に学べたのが良かったです。模擬面接を通じて、自分の強みや改善点を客観的に把握し、就職活動に活かすことができました。他者からのフィードバックは、自分では気づかなかった長所や短所を発見するきっかけとなり、自己理解を深める上で非常に役立ちました。女性だけのクラスという環境だったからこそ、キャリアに関する悩みを深く共有し、仲間と打ち解けられたのも貴重な経験です。女性限定だからこそ、女性特有の課題について共に考えることで、これからのキャリアを築く上で大切な視点を得られたと感じています。(2024年度に「キャリアデザインⅡ」女子クラスを履修・経済学部22年度生Nさん)
吹田市との官学連携PBLと産学連携PBL
1.吹田市との官学連携PBL
吹田市と連携した行政課題解決に取り組む官学連携PBL(Project Based Learning)の課題解決発表会を実施しました。この連携授業は吹田市都市魅力部シティプロモーション推進室と本学の教育開発支援センターが連携し、学生の主体的な学修活動であるアクティブ・ラーニングとして実施されたものです。2024年度は「市民部人権政策室」から、「平和について若い世代にもっと興味関心を持ってもらい、吹田市立平和祈念資料館の集客につなげていくにはどうすればいいか」との課題、「消防本部総務予防室」から、「若い人材の消防団加入促進について」との課題が提示されました。この2つの行政課題に対して、取り組んだ1年次生のグループから6件の課題解決案が発表されました。課題解決発表会に参加した全員で投票した結果、「人権賞」にチーム「大梨」が、「消防賞」にはチーム「iPhone」が選ばれ、後藤教育開発支援センター所長から記念品が贈られました。
「大梨」チームは、「吹田市立平和祈念資料館 ~認知度・来館者の増進を目指して~」と題し、発表を行いました。まず、認知度向上のためのホームページ刷新とSNS活用を提案。特に10代から30代に情報が届くようにするためのデジタル戦略として、既存のウェブサイトを最新仕様に更新し、X、Instagram、LINE、YouTubeなどのSNSで公式アカウントを開設して広報活動を強化することを挙げました。次に、館内イベントと展示の刷新について、展示コーナーの改善や、季節やテーマに基づいた企画展示の実施を提案し、3つ目として、戦時中の食事を再現する体験型ワークショップをはじめとするミニイベントの実施を検討し、リピーターを増やす仕組みを考えました。最後に、「これらの3つの取り組みを通じて施設の認知度を高めることにより、来館者数を増やすことができるのではないか」とまとめ、発表を終えました。
「iPhone」チームは、「偏りのない世代の消防団」と題し、大学生を中心とした若い世代の加入促進策を提案しました。はじめに、消防団を取り巻く現状と課題として、高年齢化が進み、若い世代が参加しづらい状況であること、また消防団の認知度が低いことについて検討した結果、若い世代、特に大学生をターゲットとした施策を考えることになりました。また、大学生をターゲットにした理由として、社会人よりも時間に縛られていないこと、「学生消防団活動認証制度」があること、体力があることなどを挙げました。具体的な加入促進策として、次の3つを挙げました。①メンターシップ制度:先輩団員とつながりを持ち、活動内容を深く理解する機会を提供する、②研修教育プログラム:学びやすい環境を整え、規範意識の向上や体験を通じた成長を支援、③フレキシブルな活動時間:時間の制約を軽減し、他の活動との両立を可能にする。これらの施策により、消防団の加入ハードルを下げ、多様な人材が偏りなく参加できる環境をめざすことができるのではないかと発表を締めくくりました。

下:消防賞「iPhone」


2.社会問題PBL
2024年度後期開講の「キャリアデザイン入門Ⅱ」の産学連携PBLクラスでは、ジャーナリストの畑山氏、シンエーフーヅ株式会社代表取締役社長 宮内氏、公認会計士・税理士の杉本氏の3名から課題提示がありました。
畑山氏からは「野生動物との共生」という課題提示がありました。最近、山から出てきたクマが人を襲うなどの人的被害がニュースになっています。過剰な山地開発と異常気象のせいで、山林に野生動物の餌が不足しているのが原因と言われています。一方、野生動物が飢えるのを心配して人が用意した餌により、猪や鹿など野生の個体が過剰に増加しています。しかし、動物愛護の観点から、動物を殺すべきではないという意見もあり、「もし自分がこの問題の行政担当者だとすれば、野生動物との共生という問題にどのように対応するか」を今回の課題としたいとのことであった。
次に、宮内社長からは「飲食業界は①どうすれば売り上げを増やすことができるか、②どうすれば経営にかかる費用を減らすことができるか」との課題提示がありました。コロナ禍で飲食業界は大きな打撃を受けました。ファストフードはあまり打撃を受けず、売り上げを伸ばし続ける一方で、ファミレスや喫茶店、居酒屋などはコロナ禍以前の水準に戻っていません。人口減少で国内市場が縮小しており、物価高騰で外食機会が減り、飲み会や会食で集まる機会も減っています。原材料費と人件費の高騰も経営を圧迫しており、飲食業は非常に厳しい環境に置かれています。しかし「飲食」は人の生活に不可欠な営みであり、生活を支える重要な産業です。自分が飲食業を営む社長ならどうするか考えてみようとの説明がありました。
最後に、杉本氏からは「企業が生成AIの恩恵を受けてどのように変化するか」との課題が提示されました。最近、上場廃止した会社のなかに、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社があります。利益が前年比7割減など、経営収支の悪化による上場廃止となりましたが、企業は外部環境に適応して利益を出し続けなければ立ち行かなくなります。一方、昨今生成AIが急速に広まり、誰でも気軽に使えるようになりました。生成AIのメリットはプロンプトを与えればそれこそ一瞬で回答できることで、うまく使えば誰もがこれまでの仕事における「作業」を生成AIにまかせて、AIにできない創造的な仕事に集中できるでしょう。一方、生成AIの回答が常に正しいとは限らず、情報源はインターネットで検索できる情報に限られます。こうした点に留意しつつ、私が提示する課題について考えてもらいたいとのことでした。
2024年12月に受講生による課題解決発表会が開催されました。
1.害獣対策について
畑山氏からの課題「野生動物との共生」に取り組んだ学生たちは、現状の害獣被害対策を調査し、今後はAIで強化すべきと提言しました。ドローンで熊の居場所や動きを把握したり、GPSで鹿・猿の生態を追跡するほか、山の木の実が豊富なら人里への出没が減る点にも着目し、AIカメラで木の実の生育状況を把握し被害を予測するなどの手法を示しました。初期費用は高いが予防が重要とし、過疎化で増す問題への継続的検討を呼びかけました。畑山氏からは、空き家被害などから問題の深刻化を予測できるので、今回の発表を機に、思考を深めるきっかけにしてほしいとのコメントがありました。
2.飲食業の業務改善について
宮内社長より提示された課題「飲食業界は①どうすれば売り上げを増やすことができるか、②どうすれば経営にかかる費用を減らすことができるか」には、提供メニューや原材料の見直しと料理研究部門の設置のほか、ガスと電気を効率的に使い、助成金を活用して太陽光発電を取り入れるなど環境負荷を減らして持続可能な事業を行うという提案を行いました。特に、SNS運用のために子会社を設立し、グルメインフルエンサーによるタイムリーで正確な情報発信で知名度を上げ、顧客を開拓しファンを増やすという提案は、宮内社長から「当社の店長会議でプレゼンテーションしてほしい」と高い評価を受けた一方、SNSをほとんど利用していない高齢の顧客も多く存在するので、そうした客層に訴求するアイデアもぜひ考えてもらいたいとの講評がありました。
3.生成AIによる業務改革について
杉本氏から提示された「企業が生成AIの恩恵を受けてどのように変化するか」という課題に対し、「株式会社ダスキン」を選び、クラス全員で取り組みました。株式会社ダスキンを選んだ理由は、掃除ロボットの普及で清掃業がAIによって大きく変わると考えたからです。AIを使えば資材や水の使用を最適化し、環境負荷を軽減できます。介護事業ではモニタリングやケアプラン作成をAIで支援し、従業員の負担を減らして質を高められるほか、会話AIで孤独感を和らげ、不安を早期に察知することも期待されます。飲食事業では無人レジやAI調理ロボットを導入すればレジ待ちの解消や人手不足への対応が進みます。初期投資は必要ですが、今後さらに深刻化する人手不足に備え、AI導入のメリットは大きいという提案を行いました。
授業担当者である松本先生の指導もあり、「野生動物との共生」、「飲食業界の抱える問題」、「生成AIが企業に及ぼす影響」という3つの課題に全員で取り組むことができました。課題解決発表会においては、産業界から直接のフィードバックがあったり、提案を喜んでもらえたりと、PBL授業ならではの醍醐味を感じることができた産学連携PBLとなりました。
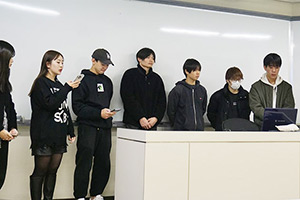



- お問い合わせ先
-
- 大阪学院大学 大阪学院大学短期大学部
- 教育開発支援センター (キャンパスマップ)
Tel :06-6381-8434(代表)
E-mail : edtc@ogu.ac.jp